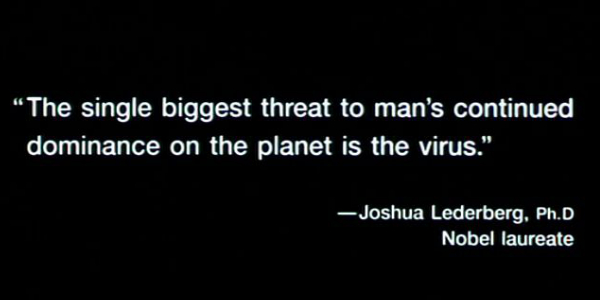次々に繰り出される圧倒的な記憶の洪水!まさしく人生とは、走馬灯ならぬ、炎を噴き上げ疾走する火車
(評価 80点)

デフォルメされた記憶のイメージが、怒涛のように繰り出され、ひたすらに圧倒される。脈絡などあろうがなかろうが構わない。何故ならそれこそが人生の真実で、稀代のアーティスト、偉大なるフェリーニの芸術そのものなのだから。
フェデリコ・フェリーニという存在と、はじめて遭遇したのがこの「フェリーニのローマ」だったように思う。その名前は、それまでにも幾度となく耳にはしていた。しかし、あくまでも堅苦しい芸術肌の監督にしか思えず、アメリカ映画一辺倒だった自分の、アンテナ圏外の存在に過ぎなかった。
そんなある日の午後のこと、ふとテレビを点けたら、その時、流れていたのがこの「フェリーニのローマ」だった。その時のインパクトは正直、度肝を抜かれたといってもいいほどの衝撃だった。映画には本来、ストーリーがある。いや、そもそも、ストーリーがなければ映画ではないという常識が、自分の中には厳然とあった。しかし、その時、自分の目の前にあったのは、記憶の断片のようなシーンが脈絡もなく連続するだけの、いわば非常識な映画だった。でも、さすがにそれだけでは驚きもしない。ただのアングラ映画として見向きすらしないはず。驚いたのは、それがバツグンに面白かったこと。

まず、イントロのフェリーニ自身の幼年時の記憶から始まって、青年となりローマに出て来る断片が描かれる、そこから本作は、それまでかろうじてまとっていたストーリーという窮屈な衣を脱いで、軽やかにストーリーを超越し、ローマという都市に対するフェリーニ自身のインプレッションが怒涛のように繰り出される。

それはまるでファンタジーの世界!エネルギーとバイタリティに満ちた都市ローマ。山盛りの食事を屋外で平らげて行く町全体がレストランのようなローマ。新たなる世代が自由を謳歌するローマ。映画の撮影隊が、ローマを目指し、高速道路を移動する。ただそれだけのイベントが、フェリーニの手に掛かれば、見たこともないようなハイウェイ上のスペクタクル・ショーに変貌する。大都市の地下で進行する掘削工事は、さながら、異星の地底世界の闇の洞窟を突き進む探検隊。やがて掘り当てた、壁画が居並ぶ空間は、時の流れから隔絶された、過去の亡霊のような人物たちがこちらを見つめる異様な、古代の異世界だ。

子供の頃、すし詰めの映画館で見た映画の記憶、大人になって連れて行かれた売春宿の記憶、週末の夜見た寄席の舞台の記憶、空襲を逃れ防空壕で一夜を過ごした記憶。豊饒な記憶の断片の数々に時系列などない。そこには、とりとめもなく、矢継ぎ早に繰り出されるシーンの数々を、ただ頭を空白にして見つめる、一種の爽快感すらある。
そして、なによりも圧巻は、クライマックスの大聖堂で、教会の司祭たちが繰り広げる世にも不思議なファッション・ショー。クラシックな伝統と奇抜でモダンなセンスが混ざり合った奇妙ないでたちの数々に目を奪われるうち、荘厳な大司教の降臨に、司教や参列者全てがひれ伏す、どこか恐ろしくもある光景を、息を呑んで見守る瞬間がやって来る、そして、夜更けの、広場で轟音を響かせ走り去っていくオートバイで本作の幕が閉じた時には、呆然と、夢から覚めたような気分にすら陥っていた。

ただの脈絡のない、断片の連続でも、そのイメージが際立っていれば、面白い映画にもなり得る。まさに、それは、人生の映画遍歴でもひときわ鮮烈な体験だった。
その後、フェリーニの代表作「81/2」の、美しいモノクロの、奔放なイメージの放流にも驚かされ、若々しいドラマ性に満ちた初期の「道」や「青春群像」といった作品群にも驚かされ、映画の世界の奥深さ、面白さにも開眼することになる。
映画には、窮屈なセオリーなどない、下手なドラマも必要ない、クリエイターの突出した才能と、のびやかな感性があれば、それがどんなスタイルであれ、それ自体ドラマになることをフェリーニは、この負け犬に教えてくれた貴重な存在なのだ。
ちなみに、あの天才スピルバーグも、他ならぬフェリーニの信奉者。まだ若き頃。あの「激突!」で鮮烈に躍り出て、その作品を引っ下げてカンヌ映画祭に乗り込んだ際には、真っ先にフェリーニのもとに駆け付け、一緒に記念写真を撮っている。その写真を見たことがあるが、いかにも大監督然とした、フェリーニの横に、あのスピルバーグが、いかにもミーハーなイタズラ小僧みたいな面構えでチョンと寄り添っていたのを今でも憶えている。
その時には、それまでのドラマ的な作風から、既に印象主義的な作風に移行していたフェリーニをはじめ、誰一人として、その小僧が、業界のビッグ1にのし上がるなど夢にも思っていなかったわけだから、人生というものは、はからずもドラマチックなものなのです。いずれにせよ、肩肘張らずとも、お定まりのドラマに飽き足らず、既成概念をくつがえすようなポップな才能に触れたい方には、オススメの作品ですよ~