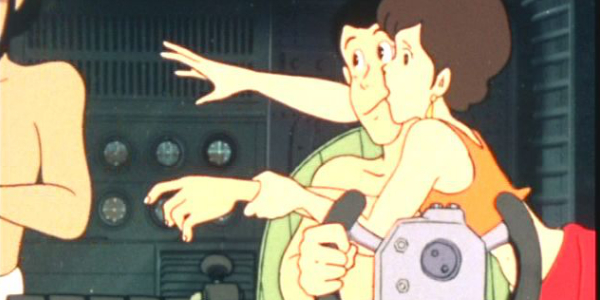新たなる紋次郎伝説のはじまり

<木枯しの音とともに再び現れた紋次郎が出合ったのは、旅に出たまま帰ってこない許嫁の相手をさがすお六という娘だった。助けを求めるお六に背を向けた紋次郎は、草鞋を脱いだ前沢一家で、お六と瓜二つの、親分の多兵衛の娘お七と出合う。二人は多兵衛の実の双子の娘だった。やがてお六が現在の育ての親とともに殺されたという報せが入り・・>
市川崑劇場「木枯し紋次郎」が終了してから四年後、当時立ち上げたばかりのテレビ東京で、紋次郎復活の企画が持ち上がる。仕掛け人はテレビ東京を全面的にバックアップしていた電通だった。しかし、紋次郎といえば、中村敦夫なくして始まらない。オファーを受けた中村敦夫は、かつて市川崑の監修のもとで作り上げたシリーズと一線を画すものを創作すべく、企画の実現に向けて動き出す。かくして、1977年10月5日の夜9時というゴールデンタイムに鳴り物入りで始まった本作を見た視聴者はのっけから呆気に取られたのだった。

呆気に取られたのは、他でもない、そのタイトルバック。このタイトルバックを監督したのが、当時「HOUSEハウス」で劇場映画の監督デビューを果たし注目を集めていた大林宜彦だった。かくいうこの負け犬も、このタイトルバックを見た時は唖然とした。それは、市川崑劇場版の、あの美しくも鮮やかな日本の美しい風景を背景にした抒情溢れるタイトルバックとはあまりにもかけ離れた、人工的でアヴァンギャルドな代物だった。

大林宜彦といえば、前身はCMディレクター。手掛けたCMも、合成を駆使した斬新なイメージで知られるところ、当然と言えば当然の成り行きではあったのだ。紋次郎の周囲で火山が噴火し、マグマが噴き上がる。モーゼの十戒の如く、割れた水面を歩く紋次郎の周囲で轟轟と滝が流れ落ちている。更には、紋次郎をアニメーション合成の蝶が取り巻き、ヒラヒラと飛び交う。そして極めつけは、紋次郎の背景にデンっと居座る花札の月、とここまでくれば、あっぱれともいわんばかりのイメージの破壊とでもいったらいのだろうか。

この数分足らずのタイトルバックの製作費は一千万。実にVシネマ一本分の製作費が投入された。市川崑劇場の大成功が、市川崑自身の監修によるタイトルバックに負うところが大きかったことを十分に意識したものだった。合成が多用される背景となる、紋次郎を含む実景パーツの撮影は妙義山山中で行われた。

かくして、装いも新たに開始された新シリーズの初回の監督を務めたのは、ロマンポルノ出身で、「八月の濡れた砂」など数々の青春映画で気を吐いた俊英、藤田敏八。大林宜彦とほぼ同世代にあたる、同監督がこだわったのは、現代劇で培ったドラマ部分のリアリズムであることは、本作を見れば一目瞭然。
顕著なのが、室内シーン。ロケを多用した屋外シーンが斬新だった旧シリーズも、屋内シーンの演出はいたってオーソドックスなものだった。しかし、本作の場合、行燈一つの照明しかない空間を意識し、それらしく、可能な限り暗いライティングで撮影が行われている。そして、クライマックスでは。一転、マカロニウェスタンばりの派手な演出、とメリハリを付けた演出で初回を盛り上げている。
かつてキー局のフジテレビとは異なる、テレビ東京という、屋台骨で開始された新シリーズ。スタッフにとっては、限られた予算と時間の制約という、もう一つの敵との新たな戦いがはじまることになるのだ。